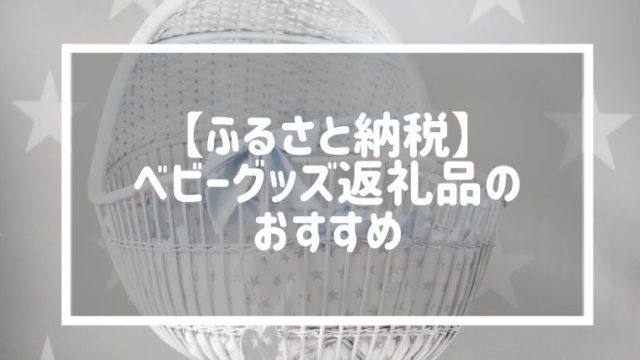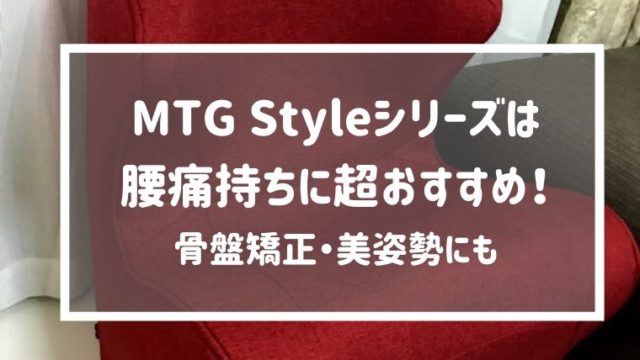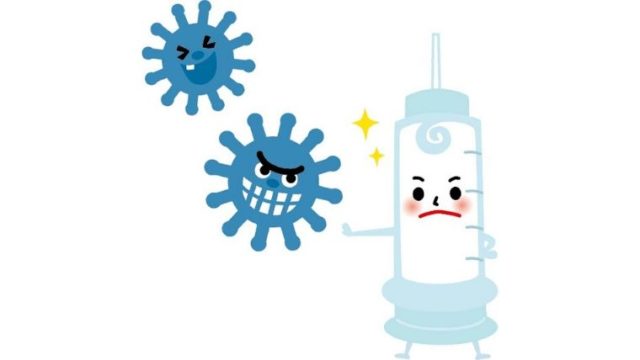長男が1歳3ヶ月を過ぎた頃、職場に復帰しました。
次男を出産したので今はまた育休中ですが、怒濤のワーママ生活を振り返って、1日のスケジュール、想像と違っていたこと、時短術、あったら便利なものなどをまとめてみました。
ワーキングマザーの1日のスケジュール

長男出産後、長いようで短かった育休が終わり、正社員(時短勤務)として復職しました。
8時間勤務が基本の会社なので、時短勤務と言っても9時出社、17時退社の7時間勤務。通勤に1時間ほどかかります。
復職後の平日のスケジュールはこんな感じです。
6:00 起床、朝食準備、自分の身支度
6:30 長男起床
7:00 長男食事、着替え、保育園の準備
7:30 家を出て保育園へ向かう
7:45 長男保育園へ
8:00 電車に乗る
8:45 会社に到着
9:00 始業
11:30 ランチ
17:15 退社、電車に乗る
18:20 保育園着
18:45 帰宅
19:00 夕飯準備
19:30 長男にご飯を食べさせる
20:00 自分とパパご飯
20:30 お風呂
21:30 長男寝かしつけ (ここで一緒に寝落ちすることも)
22:30 家事、就寝
平日はこのようなスケジュールを繰り返していました。
ひとりになれる時間と言えば、仕事中(営業職なので移動中とか)と、ランチの時間、通勤時間でした。
通勤中とランチ中に自分のやりたいことをやる!という感じです。
時間とのたたかい。朝を乗り越えるには前日の準備が大切!
ひとりの時や夫婦ふたりの時とは時間の使い方が一番変わりました。こどもが生まれてからは時間の使い方がとても大切になります。
朝は起きてすぐフル活動になるので、自分のやりたいことがある日は1時間ほど早く起きてやります。
朝、余裕をもって支度をするために、前日の夜に自分の持ち物、保育園の持ち物の準備をしておきます。
朝ごはんは、しっかり作ろう!!と思うと挫折するので、我が家の朝ごはんは炭水化物、たんぱく質、ビタミンがとれればいい!!という感じで、メニューもだいたい決まっています。
朝ごはんは1週間でローテンションするといいと思います。考える時間もなくなります。
【平日の朝ごはん例】
- 食パン、バナナ、ヨーグルト
- シリアル、牛乳、ブルーベリー
- おにぎり、みかん、豆乳
- チーズたっぷりピザパン、いちご、ヤクルト
- 食パン、セノビック入り牛乳、キウイ
保育園の昼食、夜ご飯でバランスを見て、1日の中で調整できればいいと割り切ります。
現代の文明に頼る!時短アイテムはフル活用
時短を実現するには、家電に頼るが一番。
洗濯乾燥機(ドラム型洗濯機)、食洗器は神です。
洗浄力を信じていなくて食わず嫌いのように食洗機は使っていなかったけど、試しに一度使ってから「もっと早く使えば良かった!」と後悔したアイテム。高温で洗うから手洗いより清潔だし、水道代の節約にもなった。
時短アイテムでも、ルンバなどの自動掃除機は、間取りの問題と床にものを置いている我が家には不向きだと思い却下。
仕事を始めてから、夜ご飯が遅くなることが気になったので、次に復職するときには、予約調理ができる「ホットクック」を絶対導入します。ご飯前にお腹を空かしてぐずることが多かったので、帰ってすぐ食事ができる環境が作れると帰宅後のストレスもかなり減ると思います!
自分のやりたいことは通勤中、ランチでやる!
平日のママの自由時間は、早起きして時間を作るか、通勤・帰宅中、ランチ時間のみ。
限られているからこそ、明日はこれをする!と前日の夜に決めておきます。
やりたいことをやれないことが、自分にとってかなりのストレスになることを実感。
自分で解決できるストレスの種はコントロールして芽を出させないようにします。
買い物もネットスーパー、定期宅配サービスを利用するのも手
保育園に子どもを迎えに行ってから買い物に行くのはかなり大変。荷物も多くなるし、子どももうろちょろする……。
そんなストレスは食材を配達してくれるネットスーパーなどに頼って、ストレスの芽を摘む!これなら通勤中やランチタイムに買い物を済ませちゃえる!
ネットスーパーを使うには配達エリア内に自宅が入っていないと使えないのがデメリットですが、イトーヨーカドー、
成城石井、楽天西友ネットスーパー
などで展開されています。セブンイレブンなどのコンビニでも宅配サービスをやっています。まず、自宅が配送エリアになっているか見てみるといいと思います。
また、オイシックスなどのミールキットが届く定期宅配サービスもおすすめです。私も使いましたが、珍しい野菜なども手に入って届くのが楽しみになります。帰宅後すぐ調理ができる手料理キットなどもあります。少し高いかな……と思ったこともあるけど、外食などと比べたら安いし断然栄養バランスもいいのでおすすめです。
まとめ
仕事、育児、家事とやることがいっぱいのワーキングマザー。
家族、親戚、地域サービス、時短アイテムなど、頼れるものには頼って乗り越えていきましょう!!